任意継続制度とは?
今日は前回からの続きです。
退職前に国民健康保険を調べて、高額な保険料の請求に戦慄が走りました。それでもやむを得ないと翌年の出費を覚悟していた時に、知人から
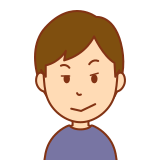
どこの健康保険組合でも任意継続制度があるはずだから、継続加入すれば保険料はかなり安くなるよ
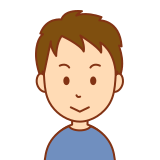
任意継続制度ってなに?
どうして保険料が抑えられるの?
任意継続制度という言葉すら知らなかった私は、すぐに出版健康保険組合のHPを調べてみました。

加入条件
健康保険の任意継続制度とは、健康保険の被保険者が、退職した後も自分の選択によって最大2年間退職前に加入していた健康保険の被保険者になることができる制度です。保険料は100%自己負担、傷病手当金・出産手当金を受けることはできないなど、在職時と受けられる内容に違いはありますが、医療費の負担はこれまでと同じ3割負担で済みます。
ただし、任意継続制度を利用して健康保険に加入するには一定の条件があります。
- 資格喪失の日の前日まで継続して2か月以上被保険者であったこと
- 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)以内に「任意継続被保険者資格取得申出書」を提出すること
加入条件は満たしていたので、国民健康保険に加入した時の保険料と比較してみることにしました。
国民健康保険と任意継続制度を利用したときの差額
任意継続制度を利用した時の保険料の算定は在職時と変わります。まず標準報酬月額は前年9月末現在における全被保険者の平均標準報酬月額と退職時の標準報酬月額のいずれか低いほうに決められます。
令和3年度の全被保険者の平均標準報酬月額は380,000円でしたので、これ以上の給与を貰っていたとしても保険料算出の基準は380,000円で計算されます。
平均標準報酬月額380,000円で計算すると、月々の健康保険料は34,200円、これに介護保険6,840円がプラスされ41,040円で済みました。
昨日と同じく、毎月の給与400,000円、年2回の賞与が800,000円ずつのケースで、国民健康保険に加入した時と比較してみます。
| 毎月の保険料 | 年間保険料 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 国民健康保険 | 65,090円 | 781,080円 | 来年の保険料は今年の所得に基づいて算定 |
| 健康保険+介護保険(任意継続) | 41,040円 | 492,480円 | 任意継続できるのは最大2年間まで |
| 差額 | 24,050円 | 288,600円 |
ご覧のように任意継続制度を利用するだけで、年間保険料が29万円近く抑えられることになります。
ただし、来年の国民健康保険は、今年の所得によって保険料が変わるため、来年の時点でどちらが保険料を抑えられるかもう一度計算する必要が出てきそうです。
保険料支払いの注意点
保険料支払いは退職した月から発生!
なお、年間保険料のシミュレーションで一点注意しないといけないのが、退職後の保険料の支払いは退職した月の分から発生するということです。給料から天引きされている保険料は、前月の保険料を支払っているためです。そのため、退職した翌月から一年間に支払う保険料は13か月分になるのでご注意ください。
それでもどちらにでも加入できるのであれば私の答えは一択しかなく、任意継続制度を利用して前職の健康保険組合に加入することに決めました。
申請は郵送でも受け付けていますが、離職票を受け取ったのがちょうど退職の翌日からちょうど20日目でしたので、受け取った当日に組合に行き直接申請しました。
申請書に必要事項を記入して15分もしないうちに新しい保険証を受け取ることができました。
これで急病を患った時にも一安心です。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
会社員時代は社会保険に加入していたので、健康保険制度について知らなくても生活できました。
年に一度健康診断を受けたり、歯医者に通ったりすることはありますが、幸いにも大病に罹ることもなく過ごしてきましたので、毎月約41,000円の支出でも楽ではないですが、国民健康保険と比べるとかなり抑えられると思います。
任意継続制度は退職後に前年の所得に基づいて高い保険料が算定される人を救済する措置でもあるため、標準報酬月額の算出に上限があるなど、所得が高い人ほどお得な制度です。
こうした情報は、前職の会社や所属する健康保険組合が必ずしもに案内してくれるとは限らず、自分自身で情報を探して申請しなければなりません。
会社員時代は自分の業務に集中していればよかったのですが、これからは保険や税金についても勉強していかないといけないですね。



コメント